宅建士の登録/合格後の流れ

宅建士資格試験に合格!だけど、合格しただけじゃダメで、登録しないと宅建士の資格をゲットできません。
なお宅建試験に合格した場合、都道府県知事に資格登録を申請できますが、登録は任意です。登録しなくても試験合格の効果は失われません。登録を行うと、宅地建物取引士証(宅建士証)が交付され、「宅建士」になります。
資格登録には、宅建試験合格、実務経験2年以上、登録の欠格要件に該当しないことが必要です。実務経験が2年未満の場合、登録実務講習を修了すれば資格登録が可能です。登録実務講習は、通信講座と2日間のスクーリングから成り、修了試験に合格すると修了証が交付されます。
資格登録の手続きでは、登録申請書、誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、合格証書コピー、顔写真、登録資格を証する書面(実務経験証明書や登録実務講習の修了証など)、登録手数料37,000円を都道府県知事に提出する必要があります。登録申請から登録通知書が届くまでには、書類に不備がなくても約2か月かかります。
宅建士の登録の流れ

宅地建物取引士(宅建士)登録の条件と手続きについては、以下の通りです。
まず、宅地建物取引士資格試験に合格することが第一の条件です。平成26年度以前の受験者は、宅地建物取引主任者資格試験が対象となります。さらに、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 宅地建物取引業で2年以上の実務経験があること
- 国土交通大臣が登録した宅地や建物の取引に関する実務講習を修了していること
- 国や地方公共団体、またはこれらの出資により設立された法人で、宅地や建物の取得・処分業務に通算で2年以上従事していること
実務経験が2年未満の場合、宅建士登録実務講習を受講する必要があります。講習修了後、登録資格が得られます。
登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 記名のある登録申請書
- 記名のある誓約書
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
- 法務局が発行する登記されていないことの証明書
- 申請者本人の住民票
- 資格証書のコピー
- 縦3cm×横2.4cmのカラー顔写真
- 実務経験証明書や登録実務講習の修了証など、登録資格があることを証明する書類
これらの書類と登録手数料3万7000円を添えて、都道府県知事へ提出します。
さらに…登録免許税9万円が必要です。
登録申請書は、国土交通省のウェブサイトでダウンロードできます。登録申請書は、記入漏れや記入ミスがないように注意して記入しましょう。登録申請書には、登録免許税の納付書が添付されています。登録免許税は、登録申請書を提出する際に、納付台で納付することができます。
登録申請書を提出する際には、登録申請書の控えを1部保管しておきましょう。登録申請書の審査には、1〜2か月程度かかる場合があります。
登録申請書が受理されると、登録通知書が送付されます。登録通知書には、登録証交付の案内が記載されています。登録証は、登録通知書に記載されている案内に従って、登録証交付窓口で受け取ることができます。
宅建士登録後、宅建士証の交付を受けることで、宅建士にしかできない業務が可能となります。これには、重要事項説明(35条書面)、重要事項説明書への記名、契約書(37条書面)への記名が含まれます。
宅建士の登録のための資格
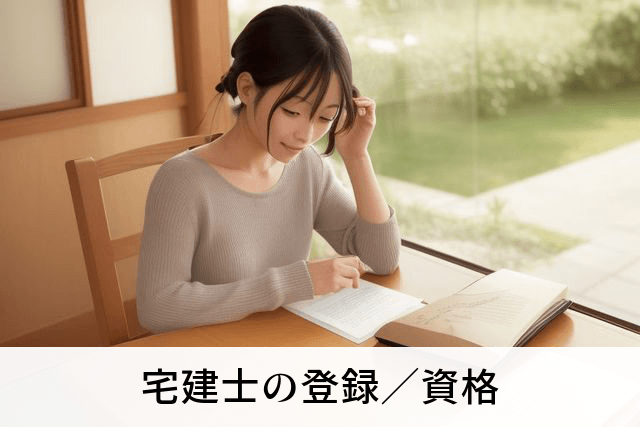
宅建士(宅地建物取引士)の登録に必要な資格は以下の通りです:
- 宅建士試験に合格していること
- 宅地建物取引業における2年以上の実務経験(不動産会社での営業職だけでなく、住宅ローンや保険の営業職も対象となります。)
- 国土交通大臣の登録を受けた宅地または建物の取引に関する実務の講習を修了(登録実務講習は、2日間の講義と2日間の演習で構成されています。)
- 国や地方公共団体、またはこれらの出資によって設立された法人で、宅地や建物の取得業務または処分業務に通算で2年以上従事していたことが必要です。
実務経験がない場合は、登録実務講習を修了している必要があります。
また、欠格要件に該当する場合は、取消しされることがあります。欠格要件には、暴力団員や懲役刑を受けたことがある人などが該当します。
宅建士の登録の必要書類と費用
宅建士登録に必要な書類と費用は以下の通りです
- 登録申請書
- 誓約書(宅地建物取引士の登録に欠格要件に該当しないこと、宅地建物取引業に関する法令を遵守する旨を誓う書類)
- 身分証明書
- 未登記証明書
- 住民票(登録申請書を提出する時点のもの)
- 合格証書コピー
- 顔写真
- 登録資格を証する書面(実務経験証明書や登録実務講習の修了証など)
- 登録手数料:37,000円
宅地建物取引士の登録申請書は、管轄の都道府県知事に提出します。資格登録申請から宅建士証が届くまでには、書類に不備がない場合でも約2か月かかります。
なお、宅地建物取引士証交付申請書への押印は不要になりました。
2022年5月18日に施行された宅地建物取引業法の改正法により、不動産取引に必要な重要事項説明書などを電子化できるようにし、書類に宅地建物取引士の押印も不要となりました。
