※当ページには広告が含まれる場合があります。
宅建の独学の試験勉強方法

高確率で失敗する独学の方法があります。
それは、小学校や中学の勉強のように、参考書などをしっかり読みこんでキッチリ理解しようとする正攻法の勉強方法。
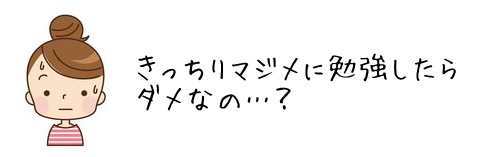
宅建を独学で合格するには、バカ正直に試験勉強しちゃダメ!
宅建士に必要な勉強をキッチリやろうとしたら、時間がいくらあっても足りません。
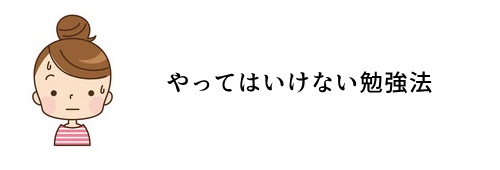
やってはいけない勉強リストはコレ。
- 教科書的なものをキッチリ読み込む…かなり効率悪い。勉強スキな人はいいかも。
- 試験直前講習…気が焦るだけ。
- 0円模試…絶対やってはいけない。合格圏内の実力ある人でも、25/50前後しか取れない難易度。
勉強すればするほど、アレも重要かも、コレも重要かも…と不安がどんどん増していきます。
0円模試はやってみるとわかりますが、合格圏内の実力ある人が自信をなくすほどの難しさ。有料コースを受講させるためにワザと難しく設定してあるんですね。じゃなきゃ、0円で公開してませんって。
過去問繰り返して自信がついてきたときに模試をやって、自信をなくす人がとても多いです。
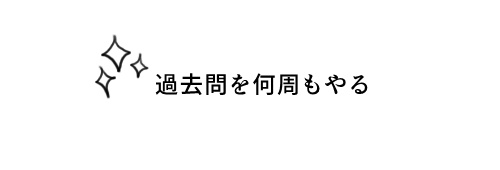
じゃあ、どうすればいいかというと、過去問だけをひたすらやるのです。少なくとも過去問をチョイと変えただけの問題は6~7割くらい出てる。下手な予想模試やるより、確実です。
試験さえ受かれば、本当の意味で理解してなくたって構わん!というくらいのゲスな考えでトライしましょう。過去問になかった問題は最初から諦めるくらいに割り切って勉強するんです。
私はこの方法で一発合格しました。
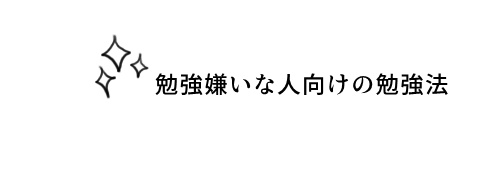
私は勉強が苦手で嫌いです。誰もしらないようなマイナーな大学卒。何の役に立つのコレ?っていう勉強は学生のころから嫌いでした。

そこで、論理的な計算問題以外は、繰り返しやって、右脳のパターン認識能力で覚える方式でトライ。このやり方は、「ひよこのオスメス鑑定士を育成する方法」に似てます。
ひよこのオスメス鑑定士って、理屈や理論ナシでパターン認識だけで判別していくそうですね。正解を知ってる人がいて、「これはオス」「正解」「これはメス」「不正解」ってのを繰り返していくと、正解率が上がっていくんだそうです。
何がどうなってたらオスとかメスとか言語化できないけど、パターン認識で判定するんですね。音楽とか絵が得意な右脳をフル活用する感じのやりかた。
そのノリでひたすら過去問を解きました。文章を読んで簡単な図を書き正誤を答えていくと、正解率が上がっていくんです。過去問をシャッフルしたオンライン問題集でも正解率が上がっていったので、単に答えを覚えてしまったというわけじゃなく、理屈ではなくパターンとして覚えたという感じだと思います。
このやり方は、私が編み出したわけじゃなくて、知り合いの資格マニアに教わりました。選択式の試験で取れる資格は、面白いようにゲットできるんだそうです。
このやり方は「勉強苦手だけど東大受かった!」という人も似たようなやり方をしてたので、有効だと思います。
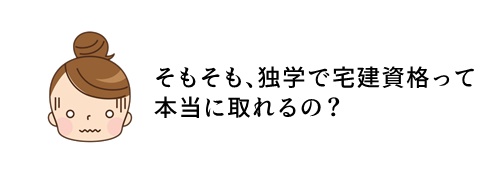
実際の合格者を見ると、宅建試験は独学でも合格することが可能ということがわかります。ただし、合格率は例年15~17%程度と低いです。やる気ないけど会社に言われて受けに来てる人とかもいるので、実際はもうちょっと合格率が高いはず。ただし、範囲が広いので、やみくもに勉強してもダメ。
独学での勉強時間は、最短で3ヶ月という人もいますが、一般的には300時間の勉強が必要とされています。
関連)宅建の独学の勉強時間
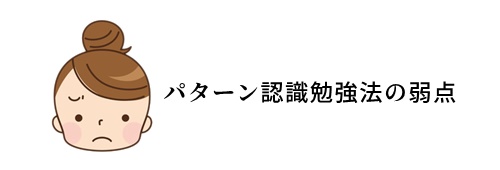
実は先ほどの「パターン認識勉強法」で解けない問題があります。間違った問題は解説を読んで、頭にイメージを描いて、そのイメージを覚えるようにしているのですが、それができないことがあるんです。
公開されている過去問題は、答えが載ってます。しかし、過去問を解いていて、「なぜこの問題、答えが3番になるんだ?1番はなぜ間違いなんだ?」って、いくら考えてもわからないケースがあります。
関連)宅建の問題と解答用紙
実は、問題を解くための大前提の知識があって、それが解説に書かれてない、とかの知らないとどうにもならないケース。
実はここが、パターン認識勉強法の弱点です。基礎をすっとばして、テストで点を取ることだけを優先しているので、基礎的な知識がちょくちょく抜けるんですね。
ネットで基礎部分に戻って調べていけば、99%は理解できるのですが時間がかかります。時間がかかると、「めんどうくさい…」「今日はつかれてるから明日」ってなって、モチベーションが下がるんですね。
そこで、「なぜ、この問題の答えはコレになるの?」「ああ、それはですね」って教えてもらえたら、時短になります。
でも、その分、お金がかかります。私は、ネットのオンライン講習についてるメールの質問サービスを使ってました。
関連)宅建は独学では無理?
宅建の勉強方法

宅建の勉強法の基本は、「過去問」です。過去に試験に出題された問題を解けるように繰り返し勉強するんですね。
時短のために、オンライン講習の質問サービスを併用するとさらに効率アップ。
当サイト管理人は、これがベストだと思っていますが、人によって向き不向きがあるかも知れません。
コツとしては、初手からいきなり過去問を解いて、「うわっ、全然できない…」という経験をすることです。ちょっと基礎をやってから過去問を解いて、いきなり良い点を取ってやろうとかスケベ心を出してはいけません。わからないとこは、適当に選んでもいいからとにかく答えを出して、採点しましょう。
最初は50点中10点くらいかも知れません。完全にランダムに選んでも4択なら確率的に12点くらいは取れます。
むしろ、最初にひどい点を取っておいたほうが楽しい。
勉強するたびに、点数が上がっていくのは、気持ちいいですよ。
文章読んでも頭に入ってこないけど、動画とか音声だとわかりやすい、という人もいます。
宅建の動画講座

本よりも動画見たほうが理解がしやすいという人は、動画解説つきの宅建講座を利用する手もあります。移動中でも見られるので、スキマ時間を活用しやすいですね。
最近人気の通信講座はこちら。
関連)宅建講座のおすすめ
低価格帯の宅建講座だと、アガルートやスタディングの名前をよく聞きます。これらの講座を受けても試験に落ちるケースも当然あるので使い方が大事ということですね。
関連)アガルートの宅建の評判
関連)スタディングで宅建に落ちた?
勉強時間が取れない…
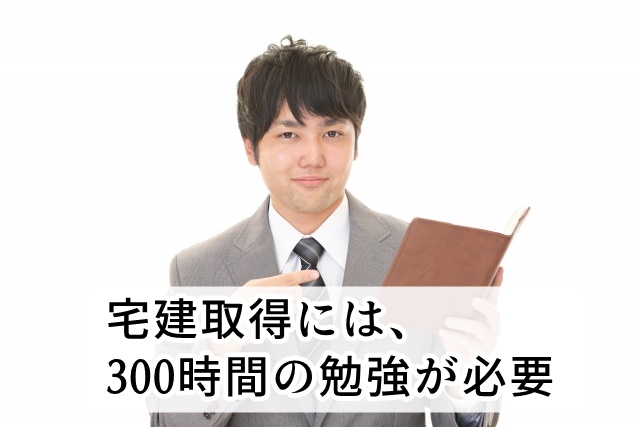
学生ならともかく、宅建取得にかかると言われる300時間を確保するのって大変じゃないですか?
私は主に、会社への行き帰りの電車の中で勉強してました。問題集と、白紙の紙を持ち込んで問題を解いてましたね。
電車の乗り換えで1本待てば座れるというラッキーな環境だったので勉強しやすかったです。
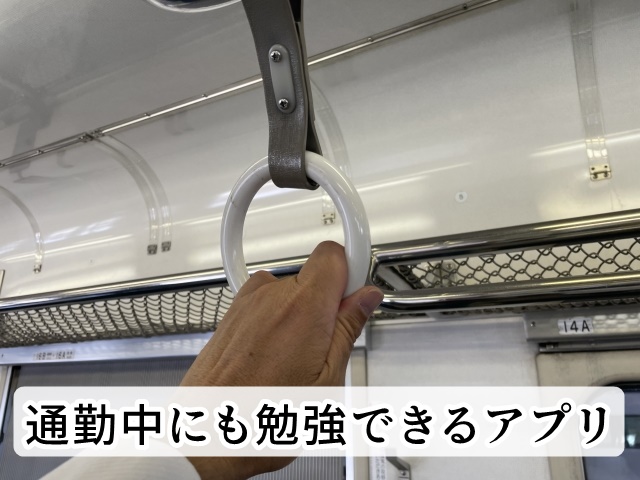
満員電車で問題集広げるなんて無理、という人はスマホアプリで勉強する方法もあります。というか、今ならほとんどのひとがアプリで勉強しているかも。
アプリは、過去問の問題の「4つの中で誤っているものはどれか」みたいな問題をバラして、この文章で述べていることは正しいか、誤っているかという2択問題にしているものもあります。
過去問やりすぎて、答えを覚えちゃったという人は、アプリを使って実力を確認してみるのもいいかもですね。
関連)宅建の勉強アプリ